|
|
 |
日時 |
平成20年5月24日(土)15-16時 |
|
 |
過食はどうしておこるか? |
|
|
|
過食とは?binge, bulimia, overeat
過食は身体面から起こるものと心理面から起こるものがある。
1.摂食調節について
1)視床下部による調節
(1)視床下部は自律神経とホルモンの司令塔
(2)視床下部に満腹中枢と摂食中枢がある
(3)満腹感と空腹感の調節は血糖値が主役
(4)拒食症では空腹感、過食症では満腹感の感度がにぶい
(5)身体面からの過食は視床下部の異常のためか?
2)大脳による調節
(1)大脳は場所により役割分担が異なる。
大脳による食欲の調節は複雑
(2)感情や気分および嗜好と関連した食欲の調節に関与
(3)過食はセロトニンの異常と関係ある?
(4)過食は嗜癖物質(エンドルフィン)と関係ある?
3)リズム
(1)寝だめ、食いだめするのは人間と家畜のみ
(2)高等や機能なので壊れやすい
(3)睡眠と食事のリズムは健康の基本
2.身体面からの過食
1)ダイエットが引き金
2)チョコレートなど特殊な食べ物が引き金
3)身体面からの過食は食事療法とリズムの調節が基本
3.心理面からの過食
1)ストレスが引き金
2)心理面からの過食は薬物療法が可能?
|
|
|
|
|
|
 |
日時 |
平成20年7月5日(土)15-16時 |
|
 |
過食にどう対応するか? |
|
|
|
1.まず身体が要求する過食に対応する
1)1日3回(朝、昼、夜)必ず食べ物を胃に送り、吐かない。食べられない時はスポーツドリンクなどでよい。
2)生活リズムを昼型にする。
3)拒食に移行しないこと。必ず反動がきて、最後には予後の悪いタイプになる。
2. 1と並行して心が要求する過食に対応する。
1)薬物療法と精神療法を併用する。
2)薬物は依存性のないSSRIを使用する。効果が出るのに時間がかかるが、過食後の落ち込みや罪悪感は取れる。過食の治る人もいる。イライラ、不安のある時には依存性のない抗不安薬を使用する。
3)精神療法には認知行動療法と対人関係療法がある。個人の性格と環境によりどちらかを選択する。
4)認知行動療法は、認知のゆがみを修正しながら間違った行動を直す。過食症によくある自己評価の低さと特有な認知のかたより(○×思考やネガティブ思考など)をホームワークの行動と感情記録を通して修正する。行動の修正のみでは再発しやすい。
5)対人関係療法は、重要な他者(親や配偶者)と自分との現在の関係に焦点をあてていく治療法である。悲哀、役割の変化、対人関係上の役割をめぐる不和、対人関係の欠如の4つの問題領域から1つを選び、コミュニケーションを中心に学習する。
3. 注意事項
1)治すのでなく、少しでもよくなることを目標にする。
2)自分で出来ることを見つけて、まず手がけてみる。
3)いったん過食モードのスイッチが入るととめる手段がない。スイッチを入れない工夫を。
4)薬物療法と精神療法を組み合わせる方がよい効果が出る。
5)ホームワークが出来るかどうかが治療の鍵となる。
6)動機付けのない人、過食に拒食と嘔吐を合併している人は治るのに時間がかかる。
7)罹病期間の長い人も治りにくいので、治療開始は早い方がよい。
8)よくなったり、悪くなったりを繰り返しながら治っていく。
9)過食が治った時、その時間をどうして過ごすか?
|
|
|
|
|
|
 |
日時 |
平成20年8月23日(土)15-16時 |
|
 |
上手にやせる食べ方 |
|
|
|
1.してはいけないこと
1) リバウンドをきたさない。
2) 過食にならない。
3) 拒食症にならない。
4) 月経をとめない。
2. むずかしいこと
1) 減量体重を維持する。
2) 太る食べ方をなおす。
3) 付き合い食を食べ過ぎない。
4) 太りにくい体にする。
5) 気分の変調(落ち込み、イライラ)をきたさない。
3.どうすればよいか?
1) 自分の体格指数(BMI)をチェックする。
2) 食事リズムを崩さない。
3) 食事回数を減らさない。
4) 食べ方の工夫をする。
5) 食事内容の工夫。
6) 酒と果物。菓子パンとチョコ。
7) インスリンダイエット。
8) 減量は10日で1kgのペースをこえない。
9) 体重グラフ
10) 月経不順となれば中止する。
11) 気分の変調があれば中止する。
12) 水分を十分にとる。
13) 運動を組み合わせる。万歩計。
14) 断る勇気を持つ。
15) ストレス食い対策。
16) さびしい人。
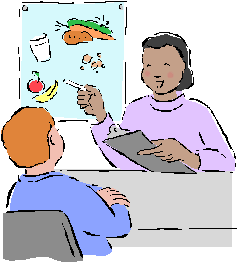
|
|